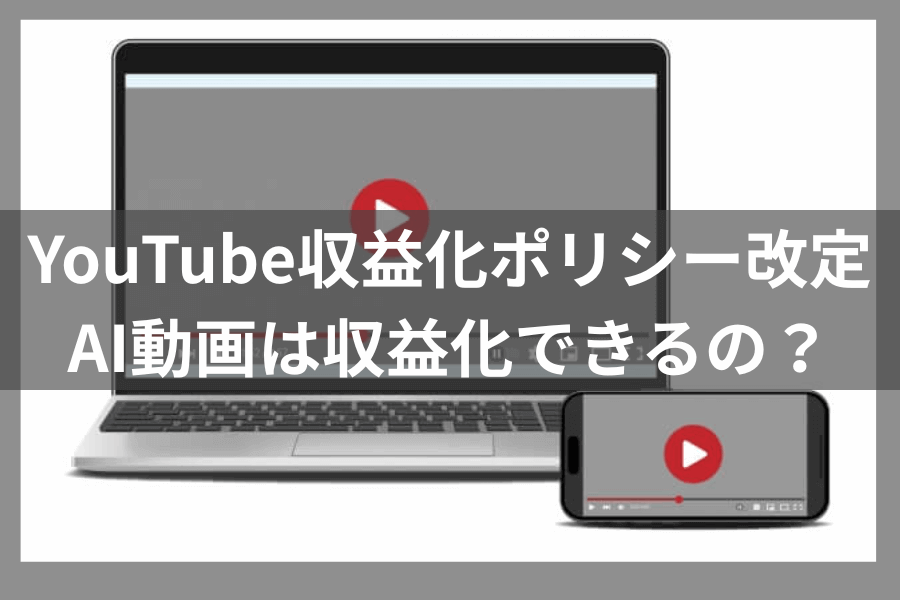
最近、「AIで動画を作ってみたけど、これって本当にYouTubeで収益化できるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実はYouTubeが、2025年7月15日から収益化ポリシーを大幅に見直すと公式に発表しています。
この変更により、特にAIを活用した動画の扱いがこれまで以上に厳しく審査されるようになると言われています。
「AIを使っただけで収益化NGになるの?」「どこまでがOKで、どこからがアウト?」
そんな声がSNSやクリエイターの間で広がっていますが、ポイントさえ押さえれば、AI動画でも収益化は十分可能です。
この記事では、実際にポリシー改定で何が変わるのかを整理しながら、
AI動画で収益化を成功させるためのコツや、やってはいけないNG例なども詳しく解説していきます。
この記事でわかること
- 2025年7月から適用されるYouTube収益化ポリシーの変更点
- AIで作った動画でも収益化できる条件とは?
- 審査に落ちやすい「再利用コンテンツ」の具体例
- AIナレーションはOK?人の声との違いは?
- 編集や構成で評価されるポイントとは
- 著作権トラブルを避けるための注意点
- 実際に収益化に成功しているAI動画の共通点
- 今後のYouTubeとAI動画の方向性
- 収益化を目指す人が押さえておきたい5つの対策
- よくある質問と回答(FAQ)
AI動画とYouTube収益化の現状
最近では、AIを使って誰でも手軽に動画を作れるようになりましたよね。
でもその一方で、「これって収益化できるの?」「審査で落とされるって本当?」と不安に感じている方も多いはず。
このセクションでは、AI動画が今YouTubeでどう見られているのか、収益化との関係はどうなっているのかを、わかりやすく整理していきます。
AIツールで“動画づくりの敷居”がグッと下がった
テキストを入力するだけでナレーション付きの動画が完成する──そんな便利なAIツールが、今ではいくつも登場しています。
アニメ風の解説動画やニュース風スライド、商品紹介なども、AIを使えば短時間で作れてしまいますよね。
この手軽さから、多くの人がYouTubeにAI動画を投稿するようになりましたが、その一方で「似たような動画が大量に投稿される」という問題も目立ち始めています。
増えすぎたAI動画に、YouTubeが“ストップ”をかけ始めた
こうした状況を受けて、YouTubeは「AI動画の増加によって、プラットフォーム全体のコンテンツの質が下がるのではないか」と懸念を表明。
そこで、AIを活用して作られた動画に対しても、“本当に価値があるコンテンツかどうか”を厳しく見極めるようになってきたのです。
たとえば以下のような動画は、収益化審査で落とされる傾向があります:
- フリー素材の映像+AI音声だけで構成された動画
- 他サイトの記事を要約・朗読しただけの動画
- テンプレート通りのスライド+ナレーションで作られた動画
- 同じ構成でテーマだけ変えた“量産型”コンテンツ
見た目には整っていても、視聴者に新しい価値を届けていない動画は、再利用コンテンツと見なされやすいのです。
とはいえ、AI動画でも収益化は可能!
ここまで読んで「じゃあAI使ったらダメなの?」と思った方、ご安心ください。
AIを使っても、動画の中に“人の工夫”や“想い”が込められていれば、収益化は十分可能です。
実際、編集や構成にひと工夫加えたAI動画で、しっかり収益化に成功しているチャンネルも多く存在します。
つまり、AIを使うかどうかではなく、
「どれだけ人が関わって、どれだけ自分らしい価値を込めているか」が重要なんです。
YouTubeの収益化ポリシーとは?
「AI動画が収益化できるかどうか」は、YouTubeの収益化ポリシーを理解しているかどうかがカギになります。
このセクションでは、ポリシーの基本から2025年の最新変更点まで、収益化を目指すなら押さえておきたいポイントを解説していきます。
YouTubeパートナープログラム(YPP)とは?
YouTubeで広告収益を得るためには、「YouTubeパートナープログラム(YPP)」への参加が必要です。
YPPに参加することで、動画に広告を表示したり、メンバーシップ機能を使ったりと、さまざまな収益化手段が使えるようになります。
YPPに申請するには、以下のような基準をクリアする必要があります:
- チャンネル登録者数:500人以上
- 公開動画の総再生時間:過去12か月で3,000時間以上
- YouTubeのポリシーとガイドラインの順守
- 2段階認証の有効化 など
このように、一定の活動実績と健全なコンテンツ運営が求められるのが、YPPの基本です。
2025年7月から「AIコンテンツ」に関するルールが強化
注目すべきは、2025年7月15日から適用される収益化ポリシーの改定です。
この改定で、特にAIを使ったコンテンツに対して、次のような方針が明確に打ち出されました:
- 単にAIで生成しただけの動画は、再利用コンテンツとして収益化不可となる可能性が高い
- AIを活用していても、人の編集・構成・工夫が明確ならOK
- 他人の著作物や発言をもとにした動画は要注意(著作権・再利用の両面から問題に)
つまり、YouTubeはAIそのものを否定しているのではなく、
“AI任せ”で中身の薄い動画に対して、厳しく見ていくというスタンスにシフトしたのです。
「再利用コンテンツ」に注意!審査落ちの原因はココにある
再利用コンテンツとは、すでにある情報や動画を編集せずに使い回したものを指します。
たとえば:
- 他人の動画をカット編集しただけ
- 音声や映像を差し替えただけのリメイク動画
- ネット記事を朗読しているだけのAI音声動画
これらは、YouTubeにとって「価値のないコピー」と判断されやすく、収益化審査で落ちる最も多いパターンです。
AIを使った動画であっても、“独自の視点”や“視聴者の役に立つ工夫”が加えられているかどうかが、収益化の可否を左右するポイントになります。
収益化されたAI動画の事例紹介
「AIで作った動画って、ほんとに収益化できるの?」
そんな疑問をお持ちの方のために、実際に収益化を達成しているAI動画の特徴をご紹介します。
もちろん詳細なチャンネル名はここでは伏せますが、どのようなポイントが評価されているのかをチェックしてみましょう。
実際に収益化されたAI動画の共通点はコレ!
調査の結果、収益化されたAI動画には以下のような共通点が見られました:
- ナレーションや構成に“人の手”が加えられている
- AIナレーションでも、台本がオリジナルで自然な言葉づかい
- テンプレートのままではなく、編集や演出に工夫がある
- コメント欄で視聴者とのやりとりが盛んで、コミュニケーション性が高い
- 情報提供だけでなく、体験談や考察など「自分の視点」が含まれている
このように、単にAIを使って機械的に作っただけではなく、「人の関与」を感じさせる要素があることが共通点でした。
逆に、収益化に失敗したAI動画のパターンとは?
一方で、審査でNGになりやすい動画にも明確な傾向があります。たとえば:
- 複数の動画が「見た目がそっくり」で、構成や話し方もワンパターン
- どこかのブログ記事をただ読み上げているだけ
- 視聴者とのやりとりがまったくなく、動画説明欄も簡素すぎる
- 編集が甘く、長すぎたり冗長だったりして“人の手”を感じさせない
こうしたケースでは、「独自性がない」「再利用コンテンツっぽい」と判断されてしまう可能性が高くなります。
ポイントは「人間の工夫や視点」があるかどうか
AIを使うこと自体は問題ではありません。
大切なのは、あなたの視点・あなたの工夫が動画の中に表現されているかです。
たとえば、以下のような工夫を入れるだけでも、印象は大きく変わります:
- 台本を自分の言葉で書く
- テロップのデザインを一工夫して視認性アップ
- 自分の経験や意見をナレーションに盛り込む
- コメント欄で「感想を聞かせてください」と呼びかける
収益化されたAI動画は、いずれもこうした“ちょっとした人間らしさ”を加えているのが特徴です。
AIツールで動画を作る際の注意点
AIを使えば誰でも簡単に動画が作れる時代になりましたが、その分「収益化でつまずいた」「審査に通らなかった」という声も増えてきています。
ここでは、YouTube収益化を目指すうえで知っておきたいAIツール使用時の注意点を、実践的にご紹介します。
AIが作る「テンプレ動画」は見破られてしまう
AIで作る動画は便利ですが、どれも似たような構成・テンポ・ナレーションになりがちです。
いわゆる「テンプレ感」が強いと、YouTubeの審査チームやAI判定ツールに「再利用コンテンツ」とみなされやすくなります。
以下のような動画スタイルは特に要注意です:
- 同じBGM・構成・ナレーションで量産された動画
- スライドと音声だけの無機質な内容
- 話し方が不自然、棒読み風のAIナレーション
- 画像・映像素材が全てフリー素材で構成されている
こういった動画は、“手軽さ”の裏にある“独自性のなさ”が審査で引っかかる大きなポイントです。
オリジナル台本と構成こそ最大の武器
「AI音声だからダメ」なのではなく、AI音声を“どう使うか”が重要です。
収益化に成功している動画は、台本の作り込みや構成に時間をかけています。たとえば:
- 話しかけるような口調で構成を考える
- 実体験やエピソードを交える
- 視聴者の疑問に答えるような形で展開する
このように、視聴者の立場を意識した「人間らしい構成」を取り入れるだけでも、収益化の可能性はグッと高まります。
編集でも“人の関与”をしっかり見せる
AIだけで完結させるのではなく、動画編集にも自分なりのアレンジを加えることが大切です。
たとえば:
- テロップや字幕にオリジナルのデザインを使う
- 無音部分のカット、BGMの挿入、効果音の工夫
- アイキャッチや場面切り替えにセンスを出す
これらの作業を加えることで、「ちゃんと人が作ってる動画だ」と認識されやすくなります。
コメント欄や概要欄でも“ひと工夫”を
動画内容だけでなく、コメント欄や説明文でも“視聴者との関係性”を意識しておくと◎。
たとえば:
- 動画の最後に「あなたはどう思いますか?」と問いかける
- 説明文で「補足情報」や「使った素材サイト」を記載する
- 投稿者としての一言を添える(例:「このテーマは初挑戦でした」など)
こうした工夫も、再利用コンテンツ判定を避けるための“人間らしさ”として評価される要素になります。
著作権とAI動画の関係
AIツールで動画を作っていると、「素材は全部フリーだから大丈夫」と安心していませんか?
でも実は、フリー素材やAI生成コンテンツにも“著作権リスク”が潜んでいることがあるんです。
このセクションでは、収益化を目指すうえで避けて通れない「著作権」の基本と注意点をお伝えします。
フリー素材でも“商用利用OKかどうか”を必ずチェック
よく使われる「フリー素材」や「ロイヤリティフリー素材」は、一見自由に使えそうに見えますが、
実際には利用条件が細かく決まっている場合がほとんどです。
たとえば:
- 商用利用NG(趣味の範囲ならOK)
- クレジット表記必須(動画の説明欄に作者名を書く必要あり)
- 加工禁止(そのままの形でしか使えない)
このような条件を知らずに使ってしまうと、YouTubeの自動検出システムに引っかかって収益化不可になることも…。
動画を公開する前に、必ず「利用規約」や「ライセンス内容」を確認しておきましょう。
AI生成素材も著作権的にグレーなケースがある
最近では、画像・音声・映像などをAIで生成するツールも多く出ていますよね。
ただし、AIによって自動生成されたものの中には、
- 元になったデータが著作権付きの素材だった
- 他人の作品と極端に似てしまった(いわゆる“AIパクリ”)
- 使用時のライセンスが明示されていない
など、トラブルになりやすいケースもあります。
現時点ではAI素材の著作権は曖昧な部分も多いため、
「出どころが明確な素材だけを使う」というのが、いちばん安全な判断です。
自作コンテンツ+信頼できる素材が理想的
結局のところ、収益化を安定させるには、
- 自分で撮った写真・動画
- 自分で書いた台本・ナレーション
- 商用利用OK&クレジット不要の素材
など、“安全なコンテンツだけで構成すること”がベストです。
「バレなければ大丈夫」ではなく、「後から指摘されない安心な動画作り」を意識することで、
継続的なチャンネル運営にもつながります。
AI動画とYouTube収益化のこれから
AIツールの進化とともに、YouTubeの動画制作スタイルもどんどん変わってきています。
そしてこれからは、AIと“人らしさ”をうまく掛け合わせることが、収益化成功のカギになっていきそうです。
このパートでは、今後の方向性について考えてみましょう。
YouTubeは「AI活用そのもの」を否定しているわけではない
YouTubeがAIコンテンツに関してポリシーを強化したとはいえ、
決して「AIを使うな」と言っているわけではありません。
むしろ最近の公式発表では、
「AIツールをうまく使えば、より多くの人が質の高いコンテンツを作れる」といった前向きな評価も明言されています。
ただし、それはあくまで「人間の意図や工夫があってこそ」。
“AI任せ”ではなく、“AIを活かす”姿勢が求められているということですね。
これからは「編集力」や「伝え方」がより重要に
今後の動画制作では、「編集力」「構成力」「語り口」など、
AIでは代替できない“人の魅力”が武器になっていくと考えられます。
たとえば同じ情報を伝えるにしても、
- 話の流れがわかりやすい
- ナレーションに感情がこもっている
- テロップや演出が丁寧で見やすい
- 視聴者の疑問に寄り添っている
といった要素があると、それだけで「このチャンネルは違うな」と感じてもらえる動画になります。
AIツールを使うからこそ、人間にしかできない工夫や表現が、より評価される時代になってきているのです。
「人×AI」のいいバランスが、これからのスタンダード
これからのYouTubeでは、
- AIに任せられるところは任せて効率化
- 自分にしかできない部分で個性を出す
というように、「人とAIのハイブリッド型」こそが理想のスタイルになると考えられます。
実際、AIナレーション+人間による編集・企画で成功しているチャンネルも増えていますし、
手間をかける部分と省く部分の“バランス感覚”がとても大事になってきています。
収益化を目指すなら押さえておきたい5つの対策
ここまで読んでくださった方なら、もうお分かりかもしれません。
AI動画でも、ポイントをしっかり押さえておけば収益化は十分可能です。
このセクションでは、これからAI動画で収益化を目指す方が、まずやるべき「5つの具体的な対策」をまとめました。
今すぐできることばかりなので、チェックしながら進めてみてください。
① ナレーションや台本はオリジナルで!
AI音声を使う場合でも、台本はあなたの言葉で書くのがベストです。
たとえば、以下のような工夫があると良いでしょう:
- 感情や語りかけのある文章にする
- 自分の体験や感想を交えて話す
- 話し方にテンポやリズムをつける
こうすることで、視聴者に「人が話しているような自然さ」を感じてもらいやすくなります。
② テンプレ動画にならないよう“工夫”を入れる
AIで作るとどうしても似たような動画になりがち。
そんなときこそ、動画の構成や演出で差をつける工夫が重要です。
- ストーリー仕立てにする
- テロップやBGMに変化をつける
- “問いかけ”や“感情表現”を交える
など、視聴者が「最後まで見たくなる」仕掛けを入れてみてください。
③ 編集のひと手間で“人らしさ”を演出
編集作業は面倒ですが、実はここが収益化審査での重要ポイントです。
- 字幕やアイキャッチにオリジナリティを出す
- 効果音や間の取り方にセンスを出す
- 冗長な部分をカットしてテンポ良く
これだけでも、「AIで丸投げした動画」とは大きく印象が変わります。
④ 著作権チェックは念入りに!
意外と見落としがちなのが、素材の利用条件やライセンスの確認です。
- フリー素材でも「商用利用OKか?」を確認
- クレジット表記が必要な場合は忘れずに
- AI生成素材も出どころが明記されているものを使う
安心して収益化するためにも、素材の扱いには慎重にいきましょう。
⑤ コメントや説明欄でも“人の関与”を見せる
YouTubeは、チャンネル運営にどれだけ本気かをしっかり見ています。
- 説明欄に補足や自分の思いを書く
- コメント欄で視聴者と交流する
- ハッシュタグや動画カテゴリも丁寧に設定
こうした“裏方作業”の積み重ねも、審査通過には大きな影響を与えるんです。
よくある質問(FAQ)
ここでは、AI動画の収益化について寄せられることの多い質問を、Q&A形式でまとめました。
YouTubeのルールやAI活用に不安がある方は、ぜひこのパートを参考にしてみてください。
Q1:AIナレーションを使った動画は収益化できますか?
A1:可能です。ただし、“人間らしい要素”が求められます。
AIナレーションでも、台本がオリジナルで自然な言葉づかいであれば、
YouTubeの収益化審査に通過した事例は多数あります。
ただし、テンプレ通りのナレーションや読み上げだけの動画は、
「再利用コンテンツ」と判断されやすくなるので注意しましょう。
Q2:AIで作った画像や映像は使っても大丈夫?
A2:原則OKですが、ライセンスや著作権の確認は必須です。
MidjourneyやRunwayなどの生成AIを使った素材は、
商用利用OKかどうか・再配布NGかどうかなど、利用規約をしっかり確認しましょう。
万が一トラブルが発生した場合、収益が止まったりチャンネル停止になるリスクもあるため、
「安心して使える素材だけを選ぶ」ことがポイントです。
Q3:既存のニュースや記事を読み上げた動画は収益化できますか?
A3:基本的にはNGと考えておきましょう。
たとえAIナレーションを使っていても、元の記事をほぼそのまま読み上げただけの動画は、
著作権の問題だけでなく「独自性がない」として収益化審査で落ちることが多いです。
自分の言葉で言い換えたり、考察・意見・補足を加えるなどの工夫をしましょう。
Q4:AIに任せすぎるとどうなる?
A4:「再利用コンテンツ」とみなされ、審査に通らないことがあります。
特に、以下のようなケースは要注意です:
- 台本がテンプレのまま
- 編集や構成に工夫がない
- 映像も音声も全部フリー素材やAI任せ
こういった動画は、「オリジナル性が低い」と判断されてしまう可能性が高いです。
Q5:収益化審査に落ちたらどうすればいいですか?
A:動画を見直して再チャレンジできます。
落ちた原因として考えられる点(再利用感、独自性の不足、著作権リスクなど)を見直し、
改善した動画で再申請することができます。
焦らず、「人の視点」「オリジナリティ」を意識して調整していきましょう。
まとめ:AI動画でも収益化は可能!大切なのは“人の関与”
AI動画だから収益化できない——そんなことはありません。
実際に、AIツールを活用しながら収益化に成功しているチャンネルはたくさんあります。
ポイントは、
- 台本や構成に“あなたの視点”を入れる
- 編集や演出に“手間”と“工夫”を加える
- 素材やナレーションの使い方に“オリジナリティ”を持たせる
つまり、AIを“道具”として上手に使いこなすことが、これからのYouTubeで収益化を成功させるカギです。
あなたのアイデアと工夫次第で、AI動画でもしっかり収益を生み出すことができますよ!